長崎市と殺処分ゼロへの取組
- Takeshi Kimishima
- 20 時間前
- 読了時間: 3分
殺処分ゼロは実現出来る!
全国ワーストの地域が殺処分ゼロへ。真剣かつ真摯に命と向き合い、全力を尽くすことで殺処分をなくすことができる素晴らしい事例があります。ぜひ、全国の自治体で一匹でも殺処分を行っているところに、この取り組みを見習っていただきたいと心から願っています。
長崎県における「殺処分ゼロ」の話題は、特に長崎市を中心に注目されています。具体的には、長崎市が2024年度(令和6年度)に猫の殺処分ゼロを達成する見込みであることが大きな成果として挙げられます。以下にその背景や取り組みについて説明します。
長崎市はかつて、猫の殺処分数が全国の中核市の中でワースト1位となる時期がありました。例えば、2003年度には長崎市動物愛護センターで約4,000匹以上の猫が殺処分されており、2009年から2017年までは9年連続で全国ワースト1位を記録するなど、長年にわたり深刻な課題を抱えていました。この状況は、温暖な気候や斜面地が多く車の通らない路地が猫にとって住みやすい環境であること、また一部での無責任な餌やりによる野良猫の増加が原因と考えられています。
しかし、長崎市は地域住民や行政、ボランティアが連携して「猫との共存」を目指す取り組みを進めてきました。その結果、2023年度には殺処分数が73匹まで減少し、ワースト7位に改善。そして2024年度には、ついに殺処分ゼロを達成する見通しとなりました。この「殺処分ゼロ」は、自然死や安楽死を除いた、行政による積極的な殺処分が行われなかったことを意味します。
主な取り組みとしては以下のものがあります。
1. 地域猫活動
野良猫の不妊去勢手術(TNR: Trap-Neuter-Return)を推進し、繁殖を抑制。長崎市は「まちねこ不妊化推進事業」を通じて手術費用を助成しています。
2. ミルクボランティア制度
2023年度から開始されたこの制度では、生後間もない子猫を市民が一時的に預かり、ミルクを与えたり健康管理を行ったりして育てる取り組みです。離乳前の子猫は手厚いケアが必要で、従来はセンターでの殺処分対象となることが多かったため、この制度がゼロ達成に大きく貢献しました。2024年度には40頭以上がこの制度で救われています。
3. 譲渡活動の強化
保護された猫を新しい飼い主に譲渡する活動を積極的に展開。ボランティアや愛護団体の協力も重要な役割を果たしています。
長崎県全体としては、まだ殺処分ゼロを達成しているわけではありませんが、長崎市の成功は県内他地域への波及効果も期待されています。例えば、長崎さくらねこの会のような民間団体がクラウドファンディングを活用して野良猫専門病院を設立するなど、県全体での意識の高まりも見られます。
このように、長崎市の殺処分ゼロは、長年にわたる地道な努力と地域全体の協力の成果であり、今後さらに持続可能な動物愛護の仕組みが広がることが期待されています。

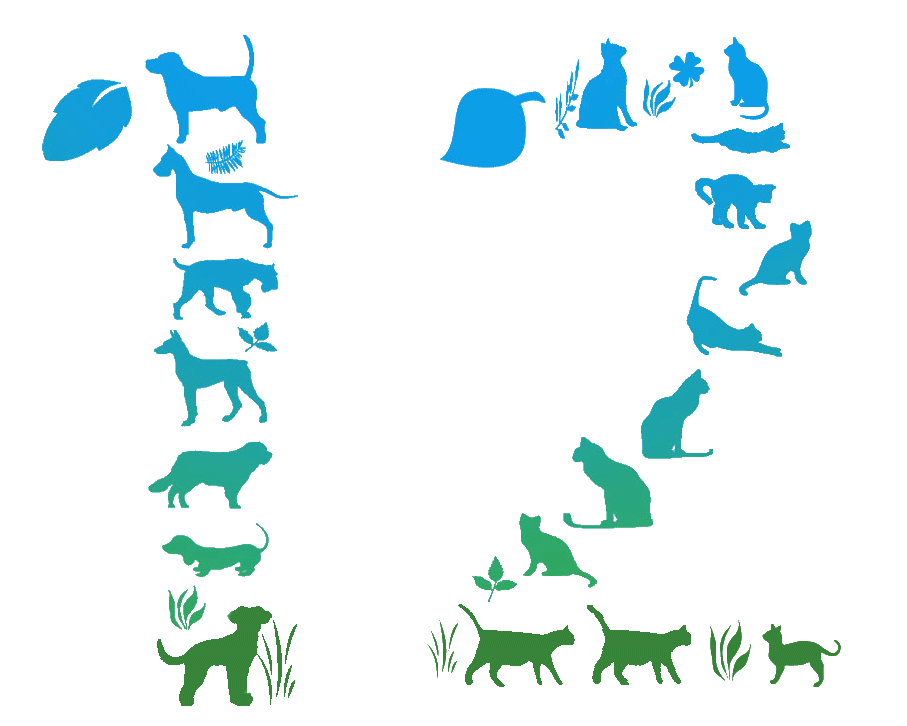







Comments