精霊の日

精霊の日(しょうりょうのひ)
3月18日は「精霊の日」と呼ばれ、柿本人麻呂、和泉式部、小野小町の3人の忌日がこの日であると伝えられていることにちなみます。ただし、彼らの正確な没日は史料に残されておらず、特に和泉式部と小野小町は生没年自体が不明です。この日は春のお彼岸の時期(3月中旬頃)に重なるため、死者の霊魂(精霊)を偲ぶ習慣と結びつき、後から3人の命日がこの日に当てられたとする説が有力です。
意味 「精霊」は「しょうりょう」と読み、死者の霊魂を指します。平安時代には和歌が文化の中心であり、仏教思想が浸透していたことから、偉大な歌人たちの霊を尊ぶ意識が強かったと考えられます。この日は、彼らの功績を振り返り、和歌を通じてその精神を偲ぶ日とされています。
背景 一説には、春のお彼岸に先祖や亡魂を供養する風習が先にあり、そこに有名な歌人たちの命日を結びつけた可能性も指摘されています。柳田国男の『目一つ五郎考』では、3月18日が歴史上の人物の怨霊と関連づけられた日として言及されており、こうした民間信仰が影響したのかもしれません。
柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)
時代 飛鳥時代(7世紀後半~8世紀初頭)
概要 『万葉集』の代表的歌人で、「歌聖」として称えられる人物。長歌と短歌の両方で優れた作品を残し、宮廷に仕えた歌人と考えられています。生没年は明確ではなく、経歴も『万葉集』の歌や詞書から推測されるのみです。特に有名な歌に「東の野にかぎろひの立つ見えてかへり見すれば月傾きぬ」(東の野に朝焼けが立ち、振り返ると月が傾いている)があります。
関連 彼の死については、石見国(現在の島根県)で没したという伝承があり、『万葉集』に「石見国に在りて死に臨みし時に」と記された歌が残されています。
和泉式部(いずみしきぶ)
時代 平安時代中期(10世紀後半~11世紀初頭)
概要 女流歌人として知られ、情熱的な恋愛歌で名を馳せました。『和泉式部日記』や『後拾遺和歌集』に多くの作品が収められています。代表作に「物思へば沢の蛍も我が身よりあくがれ出づるたまかとぞ見る」(物思いにふけると、蛍の光が我が魂のようだ)があります。生没年は不詳で、私生活も恋愛遍歴とともに語り継がれています。
関連 和泉式部の忌日が3月18日とされる明確な史料はありませんが、後世の伝承でこの日に結びつけられたと考えられます。
小野小町(おののこまち)
時代 平安時代前期(9世紀)
概要 絶世の美女として伝説に彩られた歌人で、三十六歌仙の一人。恋愛や美の衰えをテーマにした歌が多く、『古今和歌集』に収められた「花の色は移りにけりないたづらに我が身世にふるながめせしまに」(花の色は衰え、私の美も無駄に老いてしまった)は特に有名です。生没年や生涯はほぼ不明で、後世に多くの逸話が創作されました。
関連 小町の忌日も史料に明確な記録はなく、3月18日という日は伝承によるものです。
結び
柿本人麻呂、和泉式部、小野小町は、それぞれ異なる時代に活躍した歌人ですが、和歌を通じて日本の文学史に名を刻みました。「精霊の日」は、彼らの死を悼むとともに、その詩的な遺産を称える機会となっています。ただし、3月18日が本当に彼らの忌日であるかは確証がなく、後世の文化的・宗教的な解釈によるものと考えられます。この日は、和歌の美しさや儚さを味わいながら、過去の偉人たちに思いを馳せるのにふさわしい日と言えるでしょう。
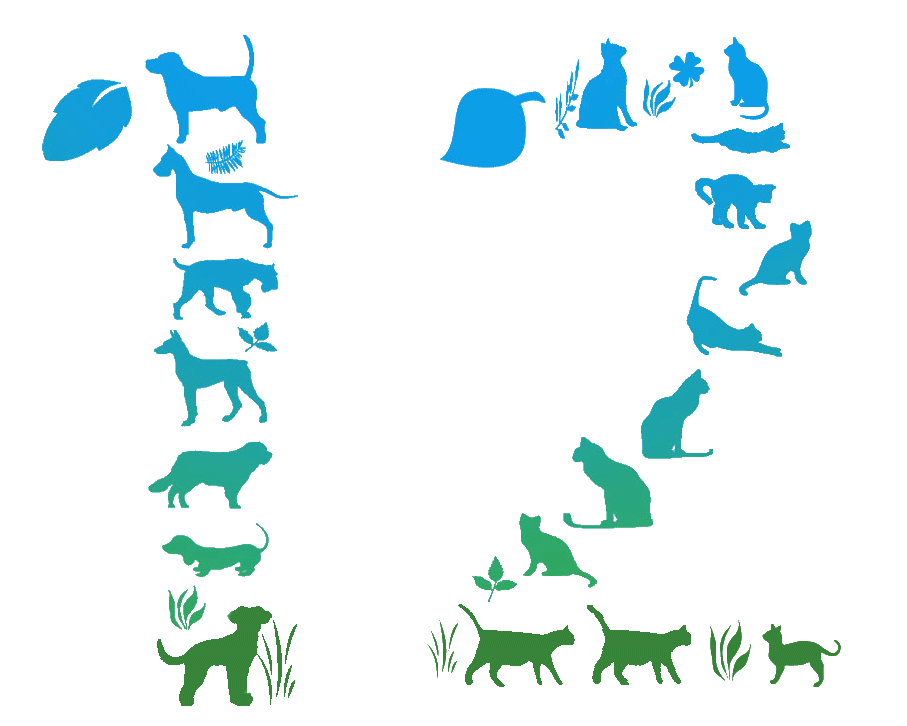






Comments